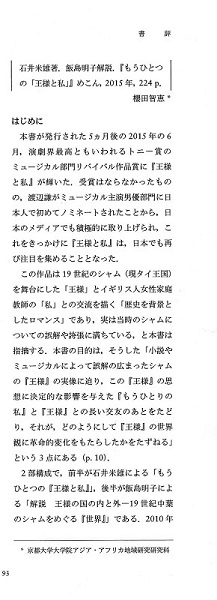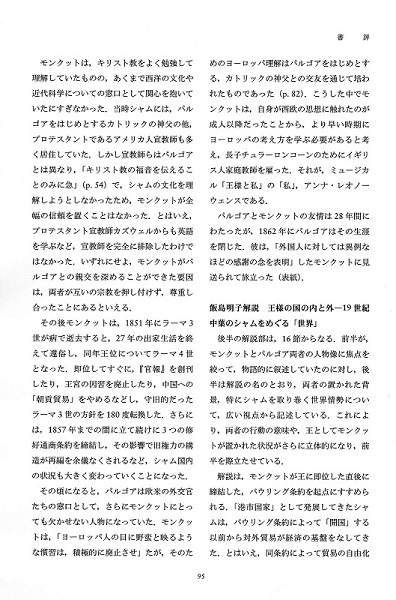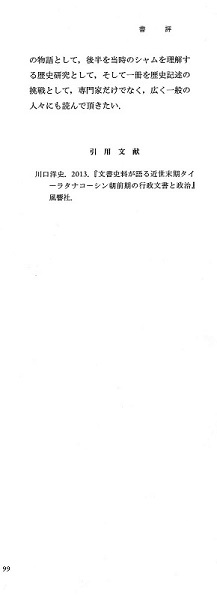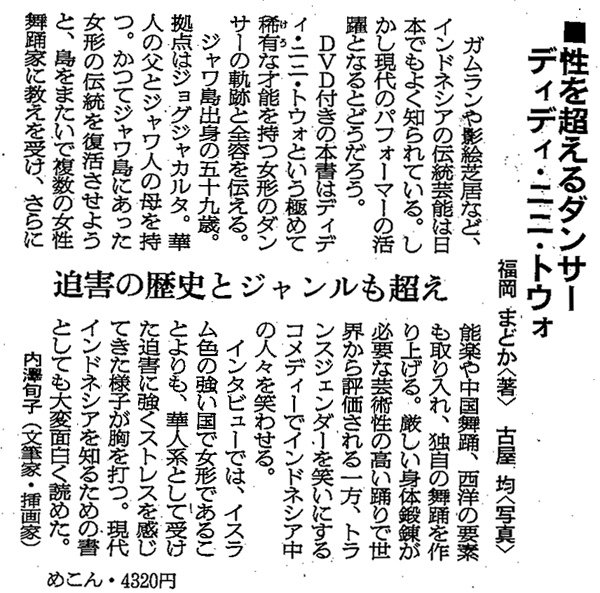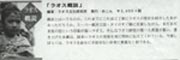|
◎赤旗 2007年11月20日 掲載
|
|
◎毎日新聞 2007年10月14日 掲載
|
|
◎2007年10月5日発行 「週刊金曜日」No673 掲載
|
|
◎2007年9月29日 「じゃかるた新聞」(インドネシアの邦字紙) 掲載
|
|
◎2007年8月14日 「北海道新聞」 掲載(ウェブ掲載許諾番号D0708-0711-00003884)
|
|
◎季刊『銀花』(文化出版局発行) No.151秋の号 2007年9月30日 掲載
|
|
◎2006年7月号 月刊『クロスロード』掲載(2006年 国際協力機構青年海外協力隊事務局発行)
|
|
◎日・タイ経済協力協会「友の会ニュース」75号2007年6月号 掲載
|
|
◎『日中友好新聞 』2007年4月5日付 掲載
|
|
◎『JTECS友の会NEWS 』Vol.73 Book & Events 掲載
|
|
◎『英語教育』(大修館書店)2007年4月号掲載
|
|
◎ALC NetAcademy 通信[32]( 2007.1.24) 掲載
|
|
◎2007年1月号 アルク「中国語ジャーナル」 掲載
|
|
◎2006年10月14日 図書新聞掲載
|
|
◎2006年07月23日 朝日新聞掲載
|
|
◎月刊オルタ 2006年5月号掲載
|
|
◎月刊クーヨン 2006年5月号掲載
|
|
◎文化人類学(旧民俗学研究)2005年70-1号掲載
|
|
◎2006年1月15日 中国新聞「読書」 掲載
|
|
◎2006年1月20日 西日本新聞「読書館R」 掲載
|
|
◎2005年11月27日 朝日新聞「読書」欄 掲載
|
|
◎2005年11月21日 産経新聞「読書」欄 掲載
|
|
◎現代女性文化研究所ニュース No.12掲載
|
|
◎インパクション149号 ブックレビュー掲載
|
|
◎季刊ピープルズ・プラン 2005年夏31号書評掲載
|
|
◎Halina「新刊書紹介」 2005年8月1日 第97号掲載
|
|
◎クロスロード「今月の本紹介」9月号掲載
|
|
◎JTECS友の会NEWS 66号 BOOK REVIEW掲載
|
|
◎JTECS友の会NEWS 66号 BOOK REVIEW掲載
|
|
◎JTECS友の会NEWS 66号 BOOK REVIEW掲載
|
|
◎アジア経済 2005.2 掲載
|
|
◎アサヒカメラ 2005年4月号 BOOK INTERVIEW 掲載
|
|
◎毎日新聞「今週の本棚」2005年7月31日掲載
|
|
◎『オルタ』(アジア太平洋資料センター)2005年4号掲載
|
|
◎J朝日新聞2005年6月15日夕刊 日本人脈記 ベトナムの戦場から③掲載
|
|
◎『JAMS News 』(日本マレーシア研究会会報)No.31掲載
|
|
◎『DACO 』158号 BOOK REVIEW掲載
|
|
◎毎日新聞2004年12月12日掲載
|
|
◎朝日新聞2004年10月24日掲載
|
|
◎読売新聞 2004年8月29日
|
|
◎西日本新聞「ASIAトゥデー」、2004年5月17日掲載
|
|
◎HOT CHILIPAPER「book release information」、7月号掲載 |
|
◎日米タイムズ、2004年2月28日掲載
|
|
◎清流、6月号掲載
|
|
◎クロスロード、5月号掲載
|
|
◎日本農業新聞、2004年2月23日
|
|
◎『農業と経済』(昭和堂発行)2004年6月号
|
|
◎Trial & Error、2004年3-4月号
|
|
◎恋するアジア、43号掲載
|
|
◎北海道新聞『世界文学・文化アラカルト/インドネシア』、2004年2月12日掲載
|
|
◎文化人類学(旧民俗学研究) 2004年69-3号掲載
|
|
◎文藝春秋「BOOK 倶楽部」、2004年4月号掲載
|
|
◎週刊朝日「本棚の隙間」、2004年3月12日掲載
|
|
◎世界週報(時事通信社)2004年8月3日号
|
|
◎じゃかるた新聞「読書欄」、3月27日掲載
|
|
◎恋するアジア、43号掲載
|
|
◎日本経済新聞「文化往来」、2004年4月1日掲載
|
|
◎読売新聞、2004年3月14日掲載
|
|
◎静岡新聞、2004年2月12日掲載
|
|
◎朝日新聞『読書』欄、2003年11月16日掲載
|
|
◎東京新聞書評欄、2003年10月26日掲載
|
|
◎四国新聞「一日一言」欄、2003年10月10日掲載
|
|
◎朝日新聞「世界の鼓動」"ぴーぷる"欄、2003年10月11日 掲載
|
|
◎じゃかるた新聞、2003年10月6日号 掲載
|
|
◎ジェトロ・センサー2003年12月号(JETRO=国際貿易機構海外調査部発行)
|
|
◎JTECS友の会ニュース60号(日・タイ経済協力協会)
|
|
◎季刊民族学』106号(千里文化財団発行)掲載
|
|
◎産経新聞、2003年6月27日掲載
|
|
◎週刊朝日、9月19日号 掲載
|
|
◎エコノミスト、2003年9月23日号 榊原英資の「通説を疑え」掲載
|
|
◎クロワッサン、11月25日号 書評欄掲載
|
|
◎東京新聞 1月30日、中日新聞2月3日掲載
|
|
◎信濃毎日新聞、2002年6月23日掲載
|

|
<マレーシア凛凛伴 美喜子著 『マレーシア凛凛』 日本をみつめる鏡として、在マレーシア十年の筆者が描くエッセー集。若いアジアの国が宿命として背負う多民族社会の風景を「暦が持つリズム」「マルチ言語」といった独特の切り口で読み解く。 昨年九月の米中枢同時テロ以降、「文明の衝突」的世界観が広がる中で、マレーシアはムスリムと華人、インド人がそれぞれの文化を調和させながら、グローバリズムにも対応して平和と成長を維持してきた。そんな生き方に「凛」という漢字を当てはめた著者の思いが共感を呼ぶ。 |
|
◎朝日新聞埼玉版、2002年1月22日掲載。
|

|
<あぶない野菜大野和興・西沢江美子著 『あぶない野菜』 「輸入野菜増加。危ないぞ日本の農業」 人々の食べ方が変われば、いま困難の極みにある日本の農業のかなりの部分が解決ないし改善されるはずである。そうした思いを込めて、野菜の現場を追ってみた。 本書は三部から成っている。第一部は輸入物に相当部分を占められてしまっている野菜を二十一品目選び、現状や問題点そしてなにより消費者が安全で確かな野菜を手に入れ、おいしく食べるにはどうすればいいか品目ごとに紹介した。 第二部は、野菜輸入背景に迫った。なぜ洪水のような野菜輸入が起こったのか、その仕組みは、主役は誰で、誰が得をしているのか。中国や韓国の野菜農民の実情にもふれながら、商社や食品企業が仕組む開発野菜の実態と構造を分析した。第三部では、ではどうすれば消費者はおいしくて安全な野菜を食べられるのかを、生産、流通、食べ方のそれぞれの側面から考えてみた。 結論は、それぞれの人が住む地域の風土に即して育てられた野菜こそが、おいしく安心して食べられるということであった。そのためには野菜の生産、流通、消費、国際交易のあり方を、これまでとは別の形に組み替える必要がある。そのためのいくつかの提言をおこない、最後に消費者が「確かな野菜を手に入れるため」の手引きをつけた。 |
|
◎信濃毎日新聞他、2001年12月9日掲載。
|

|
フィリピンで働く 日刊マニラ新聞編 『フィリピンで働く』
フィリピンに渡航する日本人が、最近増えている。日本が失った心の豊かさに、引かれる人が多いようだ。同書はそこを生活の場として選んだ人々をマニラの邦字紙の記者がインタビューした本。この国の何が人を引きつけるのかを問う。 |
|
◎旅の広場9月号 「ブックレビュー」掲載。
|
|
|
東南アジアの遺跡を歩く 高杉等著 ─アジア、その広くて深い懐─ 『東南アジアの遺跡を歩く』 カンボジアの政情が安定に向かい始めた94年、アンコール遺跡を訪れた。
青い空、うっそうと茂る緑、そして赤土色の道路が不思議なほど美しく調和する中、車は カンボジアの政情が安定に向かい始めた94年、アンコール遺跡を訪れた。
青い空、うっそうと茂る緑、そして赤土色の道路が不思議なほど美しく調和する中、車は進んで行く。
と、突然、何の前触れもなくアンコール・ワットが姿を現した。
それは、でき過ぎの演出と勘ぐってしまうほど、感動的な光景だった。
|
|
◎中国新聞、2001年4月27日(金)「時の人」掲載。
|

|
染織列島 インドネシア 渡辺万知子著 ─28年の手探りの旅結実─ 『染織列島 インドネシア』 織物会社のデザイナーとして5年間働き、「量産競争に疲れアイデアも枯渇した」1972年、インドネシア行きを誘われる。 |

|
ブラザー・エネミー ナヤン・チャンダ著 評者・丹藤佳紀(本社編集委員) -兄弟を敵にしたインドシナ戦争- 第一次インドシナ戦争は、仏領インドシナを占領した日本の敗戦直後に独立を宣言したベトナム民主共和国と旧宗主国フランスの間で戦われた。北ベトナムが南部解放を目指した第二次インドシナ戦争では、南ベトナム、次いで北ベトナムが主戦場となり、戦火はカンボジアに拡大した。 このベトナム戦争の終結とベトナム統一によってインドシナ半島にはようやく本物の平和が訪れるはずだった。しかし、事態はそうは進まなかった。二次にわたる戦争に勝利したベトナムがポル・ポト政権のカンボジアに侵攻し、中国が「懲罰」を掲げてベトナムに攻め込む第三次インドシナ戦争が勃発したのである。 この戦争は、第一次、第二次のそれとは違って社会主義を名乗る国同士が正面から戦火を交えたという点できわめて特異なものだった。本書は、「サイゴン陥落後のインドシナ」と副題にある通り、新たなインドシナ戦争がなぜ起きたかを徹底した取材と透徹した史観で究明したものである。 訳者あとがきによれば、書名の「ブラザー・エネミー」とは、敵となった兄弟を意味するフランス語を英語に直訳した著者の造語だという。 それを書名に据えた本書は、イデオロギーで美しく彩られた上辺の関係の底に黒々と横たわっていた「昨日の同志たち」の歴史的な相克・怨念が噴き出す経過を実証的に描き出した。そういえば、ベトナム国境の中国の町はかつて鎮南関といわれ、中華人民共和国になって友誼関と改称された。しかし、旧称に含まれていた大国と周辺小国の長い複雑な関係までぬぐい去られたわけではなかったのである。 こうした二国間関係に加え、日中平和友好条約とベトナム=ソ連友好条約の調印、米中国交樹立が新たな戦争の外枠となった事情も詳細に説かれ、分析に広がりをもたらした。大部な「現代の古典」の日本語版を実現した訳者の労を多としたい。友田錫・滝上広水訳。(めこん、4500円) ◇ナヤン・チャンダ=インド生まれ。ジャーナリスト。香港の『ファーイースタン・エコノミック・レビュー』編集長。 |
●2000年以前書評
【メコン川流域、アジア全域】
アジア動物誌
海が見えるアジア
東南アジアの古美術
チャンパ
母なるメコン、その豊かさを蝕む開発
緑色の野帖
メコン
【タイ】
バンコクの好奇心
バンコクの匂い
まとわりつくタイの音楽
タイの花鳥風月
タイ鉄道旅行
バンコクのかぼちゃ
タイの象
私は娼婦じゃない
バンコク自分探しのリング
タイ人と働く
タイ人たち
蛇
【ラオス】
メコンに死す
【ベトナム】
ハノイの憂鬱
ベトナムのこころ
ベトナム革命の内幕
女たちのベトナム
パリ ヴェトナム漂流のエロス
はるか遠い日
【カンボジア】
ポル・ポト伝
カンボジア・僕の戦場日記
【インドネシア】
ワヤンを楽しむ
ハッタ回想録
おいしいバリ
インドネシア全27州の旅
インドネシアのポピュラーカルチャー
日本占領下インドネシア旅芸人の記録
人間の大地
すべての民族の子
足跡
香料諸島綺談
ナガ族の闘いの物語
電報
渇き
カルティニの風景
ジャワの音風景
アルジュナ、ドロップアウト
【フィリピン】
フィリピン・インサイドレポート
七〇年代
仮面の群れ
【ミャンマ】
北ビルマ、いのちの根をたずねて
【台湾】
さよなら再見
【インド】
ペシャワール急行
焼跡の主
マレナード物語
焼身
デリーの詩人
【日本とアジアの関係】
アジア定住
新宿のアジア系外国人
チョプスイ─シンガポールの日本兵たち
 2000年以前の書評はこちら
2000年以前の書評はこちら