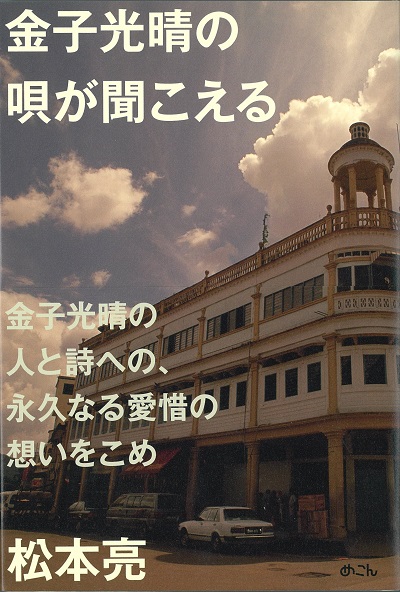
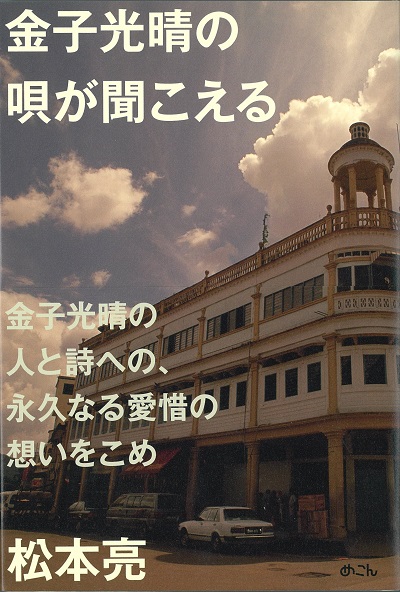
|
松本亮さんは金子光晴と最も親しい友人でした。本書は、金子光晴の死後、雑誌『新潮』に掲載された同名のエッセイに加筆したものです。しかし、今年3月、あとがきを書きかけて、松本さんは急逝されました。
【目次】
バトゥパハの女
森三千代のこと
土方定一のこと
流浪の意味
山中湖畔の宿
R子のこと
『愛情69』以後
書きかけのあとがき
松本亮の優しさ(暮尾淳)
【書きかけのあとがき】
「金子光晴の唄が聞こえる」は、雑誌『新潮』の一九八三年(昭和五十八年)四月号に、三五〇枚一挙掲載ということで発表された。その後まもなく単行本化されるはずのところ、事情により、そのまま三十数年が経過した。
あっというまだといえば、それまでで、まあ、そんなものかと思ってもいたのだが、ここへきてマッちゃん、マッちゃんと金子の呼ぶ声が聞こえる。考えてみれば、私がもう金子大兄より一〇年も余分に生きていることで、なにか忘れてやしませんかというわけである。そんなことで一寸慌てこの本がやがて遅まきの初版本として世に現れることになった。他意はない。
本意なのかどうか、葬式なんかいらん、俺のことなど研究してくれるななどと折に触れてはいっていたおどけの“金子さん”。そうなんだよね。研究されなくても、エロじい、ふうてん老人、といった風評がいまだまかりとおっている反骨の大詩人。なんの縁か、すさまじい最後の二五年間、そのそばであれこれを見させてもらうことともなった。金子光晴万華鏡の一端をしるし、その生きざまのよけいなことをかきおって、何ほざいとるといったところもあるかしれないけれど、まあご勘弁のほどを。
(2017年3月7日、著者が倒れる直前にかきかけたもの)
【本文より】
バトゥパハの女
マレーシア人の運転する車にのって、三人の女性を道連れに、からりと晴れあがったクアラルンプルの午下りをあとにした。市街地の混雑をやりすごしたころ、助手席にいた私は運転手に話しかけた。「バトゥパハまで何時間くらいかね。」「まあ三時間か五時間だね。」なぜ四が抜けおちるのか奇妙に思ったが、それにはかまわず私はひとりごとのようにして呟いた。「ゆっくり走っておくれ。別に急ぐ旅でもないんでね。」
急に視界がひらけた。舗装された道がまっすぐにのび、その左右には大王椰子が道を蔽ってそびえる。葉先が青空を繊細に截ちきって美しい。
金子光晴が昭和五十年六月、七十九歳の生涯を閉じた、その年の暮のことだった。葬儀を終えてほっと息をつき、何か忘れものをした想いにかられて金子の著書を手にとり、あらためてつぎの文字を眼にしたとき、私はしまったとほぞを噛んだのだ。
〈そうだ。僕はまだ、バトパハにいるのだった。おそらく、僕の友達が二百人いるとしても、これから先もそのうち一百九十八人は知らないで終わるにちがいない、そのバトパハにいるのだった。〉(『西ひがし』より)
横面を張られた衝撃が全身をはしった。なぜ生前に私はあのバトパハを訪れることをしなかったのだろう。〈山川の寂寥がバトパハぐらいふかく骨身に喰入るところはなかった。〉(『マレー蘭印紀行』より)とも彼は記す。そのあふれる想いはさらに晩年の自伝小説『西ひがし』で増幅されて、哀感にみち、それじたいが彼の生涯の背骨を支えて立ちあがってくるかとみえたのである。
つかず離れずだったが、その生涯の最後の四半世紀を、その行動、作品活動のあれこれにじかに接しえた私には、マレー半島南部のマラッカ海峡に面する小さな海村バトゥパハが、金子とのかかわりにおいてもっとも気にかかる土地とはなっていたのである。ふだんの金子の話題にのぼることがなかったので、そのままにすぎたのだが、彼の厖大な作品群の中で、この海村にかんする描写ほど愛惜の想いにみちて書きこまれている土地は他になかった。
しかも南方の風物はこの時期の私にはもはや珍しいものではなかったのだ。数年前から何度かインドネシアのジャワ、バリ島を往来しては、そこに根を張る影絵芝居を追い、さらに関連のあるマレーシアの影絵芝居を求めてクアラルンプルまでは足を運んでいたのである。しかしそこからさほどでもないバトゥパハに私はなぜか立ちよることがなかった。
バトゥパハへゆこう、私はそう思った。ほぞを噛む思い、しかしその思いは羽田をとび立ったあとはどこかへ消えていた。その土地をみて、私は何をしようとするのだろう。金子がそこでパリへの苦痛にみちた道すがら、束の間の息抜きをすることができったのであったにしても、すでに四十六年をへた今の時点で、私は何を見ることができるのだろう。
この車は日本製だ、と運転手はいった。うん、知ってるさ、と応じる。車は滑らかに走り、大王椰子の並木は途絶え、そのあたりから、みごとなゴムの農園がつづく。この道は四十何年か前、金子が乗合いタクシーにゆられて走った道だ。三十何年か前には日本帝国軍隊が侵略の鉾先をシンガポールへむけ、銀輪部隊をつらねて南下した道でもある。諸所で戦いがあったのだ。ということは日本人の手により無辜の人間の血が無残にその大地に吸われたということである。
金子はクアラルンプルでは、四十歳をこした日本娘たちが客をつれこむ部屋貸宿の一室に泊り、その宿をきりもりする島原なまりの老女から〈彼女の友人達のおちこんでいった凄惨な末路や、怖ろしい「蟻地獄」のこと〉をきき出している。それは「コーランプルの一夜」にまとめられて、天草、島原の女たちが女衒の手に売られ、南方瘴癘の地を稼ぎ高につられてさらに奥地へ、また名もない小さな島のはてまでも落ちていったさまを、克明にしるしている。
そのとき金子自身もまた彼女らの境涯とさほど変わることがないと身に沁みて感じたのである。それは私のような表敬訪問の旅、また今日の文化人類学者や流浪人研究者らがいわゆる調査のためその土地々々を訪問して歩くといった体のよさは微塵ももちあわせていなかった。彼はそれらの土地に日本人を訪ねては懐中にした水彩絵具一式をたよりに、頭をさげて似顔絵を描かせてもらい、何がしかの金銭を得るためのひとり旅をつづけたのだ。いつどこで野たれ死にするかしれなかった。しかもその日その日をやりすごせばいいわけでもなかったのである。愛妻森三千代はひとりシンガポールからパリへの船上にあり、彼はそのあとを追わねばならなかった。パリまでの船賃ははした金ではなかった。彼は「苦しかったこと」という一文にこう記している。〈シンガポールを出発する以前から、デング熱という風土病にかかって、二週間ほど旅館で高熱を出して、果物の汁だけすすっていたので衰弱し、四十五度の南方の炎天下に立つと気が遠くなって倒れそうになった。シンガポールの対岸のマラヤのジョホール州の首府ジョホール・バルーから出発して、マラッカ、タイピン等を経てスレンバンという町に着いたときは、ゴム園やジャングルを歩いてきたために、マラリヤ蚊に刺され、毎日一定の時間に悪寒とふるえがはじまって、苦しまねばならなかった。(中略)私は、この旅の途中で斃れてしまうのではないかと幾度もおもった。南方のけしきは、見渡すかぎり荒寥としていた。〉
私たちの車はみごとに整理されて道の両側にたたずまうゴム園を突ききり、スレンバンという名の町を通過していた。スレンバンは賑やかな小都市である。その賑わい、またゴム園のたたずまいは、しかし四十幾年か前とさほども変わっていないと思われる。むしろ合成ゴムが幅をきかす今日よりも英国植民地時代の当時のほうがはるかにゴム園は整備されていたはずである。自動車の走る道路状況もまず似たようなものだろう。意に染まぬ似顔絵師という特殊な境涯になければ、金子もまた〈南方のけしきは、見渡すかぎり荒寥としていた〉などとは書かなかったのではないか。いったいに風景描写というものは筆者のそのときどきの心象をうつすものといわれるが、金子の場合もこれに洩れず、南方の豊潤の緑、なつかしい土のむせかえる香り、さらには暑熱をやわらげる強烈な驟雨(スコール)も、多くの場合、彼を脅かすもののけとうつった。そこには虎や蠍やコブラがいたかもしれないが、常時人間に狙いを定めて襲撃をたくらんでいたわけのものでもない。鬱々とした旅のつれづれに、その見聞はこまかくノートのはしや紙きれに書きとめられて、それが彼の強靭な文章の骨格として生きたのだが、そこにまた金子の生来の気弱さやデリカシーがのぞけてもいるのである。彼は前掲の文章の末尾をこう結んでいる。〈あの旅は旅と言うよりも地獄廻りのようなものであった。そんな旅でも、旅は道づれという言葉の通り、誰か友達がいっしょだったら、苦しみを半分に分けてなぐさめあうこともできたろうにとおもう。しかし、苦しかったことも、過去のこととなれば、人間は苦しみは忘れて、たのしいおもいでだけが残るという気楽な本性をもっているもののようだ。〉
おそらくは金子もまた〈地獄廻りのような〉旅の中で、人情の機微にふれてこころ温まり、旺盛な繁茂をしめす熱帯植物群の細部を凝視し、平手打ちくらわす豪雨と底しれぬ天の青さ、そして身も心も腐るかと思われる高温多湿の中のけだるさをそのままにたのしみ、ときには身の境遇をも忘れていることのできる時刻ももてたはずだ。・・・
【著者はこんな人】
松本亮(まつもと・りょう)
1927年、和歌山県に生まれる。
1948年、大阪外国語大学フランス語学科卒。
1951年、詩人金子光晴を訪ね、同氏没年(1975年)まで親交をつづける。
1953年、バレエ「白狐」(台本、演出)を松山バレエ団により上演。一九七〇年「高野聖」なども。
1968年、はじめてインドネシアを旅し、ワヤン上演を見る。
1969年、日本ワヤン協会を設立。以降、没年まで主宰する。
1998年、インドネシア共和国大統領より文化功労勲章を受ける。
2017年3月9日、多臓器不全で死去。
著書:『運河の部分』『ポケットの中の孤独』『人間、吹かれゆくもの』〈以上詩集〉。『アンコール文明』『ジャワ影絵芝居考』『マハーバーラタの蔭に』『ワヤン人形図鑑』『ジャワ夢幻日記』『悲しい魔女』『ラーマーヤナの夕映え』『ワヤンを楽しむ』『新雑事秘辛(金子光晴との対話集)』『ジャワ舞踊バリ舞踊の花をたずねて――その文学、ものがたり背景をさぐる』ほか。